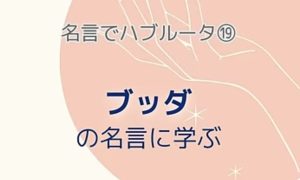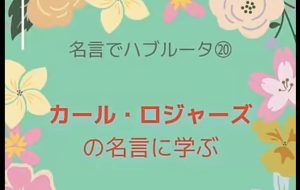早朝の親子ハブルータ

2025年前期を終えながら…最近の我が家の話を書いてみます。
数日前、朝ベッドで目を覚ました子どもたちと、ふとしたきっかけで交わした会話…
(うちの子たちは、時々ふいに本質的な話を私に投げかけてくることがあります。それだけに、母として常に心の準備をしていないといけないなと感じます。)
朝ベッドで目を覚ました子どもたちとの会話
娘(中学2年):
「ママ、うちの学校の歴史の先生は30代の若い女性なんだけど、“反日本主義”だって授業中に言ってたよ。日本が本当に嫌いなんだって。だから日本には行ったこともないし(行きたくもないって)、数年前の日本製品の不買運動にも積極的に参加したんだって。」
私:
(内心、“今どきそんな話をする先生がいるんだ…”と驚きつつ、できるだけ冷静に)
「そうなんだ。その先生は、ママが日本人だって知ってて、そういう話をするの?」
娘:
「ううん、知らないよ。でも私が日本人(娘は時と場合によって、自分を韓国人とも日本人とも言う…笑)だって知ってる子たちが、私の表情をうかがってて…それがちょっと嫌だった。」
息子(小学生6年):
「うちの先生は、僕のお母さんが日本人で、僕が日本に住んでて日本語が話せるって知ってて、わざと質問してくるときがあるよ。自分も日本語ちょっとできるって自慢したいみたいで、僕に話しかけてくるのが本当に嫌なんだよ…放っておいてほしいのに。」
私:
(ユナに向かって)
「小学校低学年のとき、独島(竹島)の授業で聞いた言葉がショックだったから、担任の先生にお父さんが電話してくれたでしょ?あのときみたいに、今回もお父さんに話してもらおうか?お母さん(=当事者)よりも、韓国人であるお父さんの方が、“多文化社会で育つ子どもたち”の立場として、うまく話してくれると思うんだけど。」
娘:
「ううん、大丈夫。私はその歴史の先生の個人的な意見として尊重することにしたよ。ただ日本のことをよく知らないだけだし、大ごとにしたくない。」
息子:
「僕も、うちの先生が(日本を好きな立場だけど)僕にやたら話しかけてくるのは…今度から不快だって言おうと思ってる。そして、お姉ちゃんの言う通り、人それぞれいろんな意見があるのが当たり前だし、僕たちもそういう人たちを受け入れないといけないと思うよ。」
ハブルータ(対話教育)の力
私は内心でこう思わずにはいられませんでした。
「わあ…本当にうちの子たち、大きくなったんだな…。
どうしてそんなに成熟した考え方ができるんだろう?」と。
もう、ママやパパの助けがなくても、
自分の足で立ち、
自分の言葉で表現し、
広い心で学校という社会の中で人と関わる術を
身につけているんだな、と感じました。
そんな話を朝7時に交わして…
その日は一日中、嬉しくて誇らしくて、夫にもすぐにメッセージで報告しました。
これが“ハブルータ(対話教育)の力”なのかな?とも思いました。
国際家庭の子どもとしてのアイデンティティを受け入れ、
2つの国を超えて、もっと広い世界への愛を育んでいく子どもたちであってほしいと、
心から願っています。